

![]()
精神上の障害により判断能力が不十分なため契約等の法律行為おける意思決定が困難な成年者(認知症・知的障碍者・精神障害者等)について、家庭裁判所が選任した後見人等の援助者が本人の意思決定を代行したり、本人の意思決定に同意することにより判断能力を補い、本人の権利を守る制度です。
成年後見には法定後見と任意後見があり、その他民法上の委任契約に基づく財産管理委任契約もございます。
![]()
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、本人を代理したり、本人の法律行為に同意をしたり、取消権を行使することによって本人を保護する制度。
![]()
本人が一人で日常生活を送ることができず、一人で財産管理等をすることが困難な状態です。
![]()
家庭裁判所に後見開始の申立を行い、成年後見人が選任された場合、成年後見人が広範な代理権及び取消権を行使することにより本人を保護します。
![]()
本人が日常的な買い物程度は一人でできるが、金銭の貸借や不動産の売買等、重要な財産行為は一人でできないないといった、本人の判断能力が著しく不十分な場合。
![]()
家庭裁判所により一定の重要な行為(預貯金の払戻し、金銭の貸付け等)を行う際には、保佐人に同意・代理権が付与されます。
![]()
本人が一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安があり、本人の利益のために誰かに援助してもらった方がよいというように、本人の判断能力が不十分な場合。
![]()
家庭裁判所により、本人が望む一定の事項についてのみ同意、取消および代理権が付与され、補助人はこれを適切に行使することにより本人を援助する。
![]()
事理弁識能力に問題がない時点において、精神上の障害により事理弁識能力が不十分になったときに備え財産管理等のあり方を決定し、その決定に従って財産を管理する制度。
![]()
精神上の障害により事理弁識能力が不十分になったときに、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時から効力が発生する.。
※任意後見契約を締結する場合、公正証書によって作成する必要があります。
![]()
本人の希望を実現するため、原則として任意後見が法定後見に優先します。
但し、任意後見契約に定められた条項により本人の保護が不十分となった場合、法定後見の申立が必要となる場合もございます。
![]()
委任者が受任者に対して自己の財産管理に関する事務の全部又は一部を委託し、委託した事務について代理権を付与する委任契約
![]()
①判断能力に問題はないが、身体上の障害から財産管理を自分で行うことが困難な場合も利用が可能です。
②任意後見契約と一体で結ぶことにより、判断能力が十分あるときから継続的な本人の保護を図ることが可能となります。
![]()
①継続的見守り条項
定期的に面接などの方法によって本人の身上の確認をすることを内容とする条項
②法的アドバイス条項
日常生活に係る問題について司法書士の業務の範囲内で必要に応じて法的助言を求めることができる条項
③死後事務委任契約
死亡前に負担した債務の支払、身の回りの生活用品の処分、葬儀・埋葬に関する事務等について委任する契約
成年後見に関してお困りの方はご気軽には当事務所にご相談してください。
更に詳しい成年後見の制度についての知りたい方は、下記ホームページも合わせて参照してください。
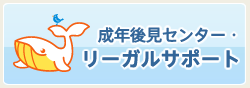
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()