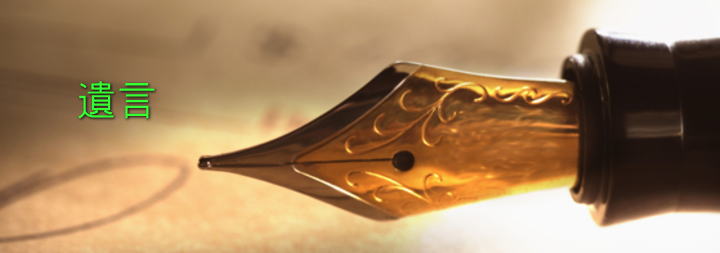
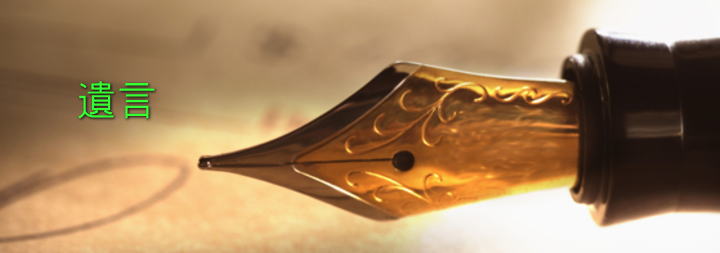
![]()
遺言とは、遺言作成者が、死亡後の自己の財産に関し最終意思を表示した場合には、その意思を尊重するという制度です。
![]()
普通時方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、特別方式の遺言には危急時遺言、隔絶地遺言があります。

![]()
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆し、押印することによって作成する遺言です。
![]()
①作成自体について費用がかからない方法である。
②遺言の存在及び内容を秘密にすることができる。
③手軽に作成することができる
![]()
①遺言書が発見されない恐れがある。
②発見した者によって偽造、変造、隠匿及び破棄される危険が高く、不十分な内容であると意思が実現できない。
③家庭裁判所の検認手続きが必要であり、遺言を執行するについて新たな費用と手続きが必要である。
![]()
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。
![]()
①公証人が原本を保管するので偽造、変造、隠匿及び破棄のリスクはほとんどない。
②家庭裁判所での検認手続きを経ることなく、迅速に遺言を執行することができる。
③将来遺言の内容について紛争が生じる危険性は低くなる。
![]()
①遺言内容が証人等に知られてしまう(但し、守秘義務が課せられた者に証人を依頼すれば第三者に内容が漏れる危険性は低くなります)。
②公証人との間の手続きが面倒であり費用もかかる。
③2人の証人を用意する必要がある。
![]()
遺言の内容自体は秘密にし、その遺言書が存在することを公証人により公に記録してもらう方法による遺言です。
![]()
①公証人が関与することにより本人の作成した遺言であることは証明される。
②遺言書の存在について明らかにしながら、遺言の内容を他者に秘密にできる。
③自署能力がなくても、パソコンやワープロを使って作成することができる。
![]()
①公証人に対する費用や証人を2名用意する必要がある。
②公証人は、遺言内容については関与しないことから、内容的に問題があっても是正の機会が与えられない。
③遺言書の検認手続きが必要である。

![]()
危急時遺言は、遺言者が死亡の危急に迫られた場合においてなす遺言の方式です。
危急時遺言には、一般危急時遺言と難船危急時遺言があります。
一般危急時遺言は、疾病その他の事由によって死亡の急に迫った者が証人3人以上の立会のもとなされる遺言です。
難船危急時遺言は、船舶が難船した場合において当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者が証人2人以上の立会いのもとなされる遺言です。
![]()
①口頭遺言の許容
②家庭裁判所の確認(一般危急時遺言は「遺言の日から20日以内」、難船危急時遺言の場合は「遅滞なく」)が必要である。
![]()
隔絶地遺言は、公証人を利用できない場所にいるためため公正証書遺言や秘密証書遺言を作成することができない場合に作成できる遺言です。
隔絶地遺言には、伝染病隔絶者遺言と在船者遺言があります。いずれにおいても自筆証書遺言を作成することはできます。
伝染病隔絶者遺言は、伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に存在する者が、警察官1人及び証人1人以上の立会いのもとなされる遺言です。
在船者遺言は、船舶中に在る者が、船長または事務員1人及び証人2人以上の立会いのもとなされる遺言です。
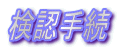
![]()
検認とは、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための一種の検証手続であり、証拠保全手続です。
公正証書以外の遺言書の場合検認手続が必要です。
![]()
相続人が、公正証書以外の遺言を発見する。
![]()
家庭裁判所に対し、検認申立書とともに、遺言者・相続人全員そして申立人の戸籍謄本や除籍謄本をあわせて提出する。
![]()
申立人及び相続人は、家庭裁判所に指定された検認期日に出廷し、遺言書を保管している者は遺言書を持参する。
![]()
家庭裁判所は、申立人の立会いの下で、遺言書を開封し、遺言書を確認して検認調書を作成する。
当事務所においては遺言作成、検認手続のサポートを行います。遺言に関しお困りの点がございましたら当事務所にご相談してください。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()